総合政策 2016年
[解説]
問1……
(1)国際比較(2)職業の世代間移動(3)高齢化、という三つの視点のうち、比較的格差について書きやすいのは高齢化についてである。高齢者は若年層と違い格差が如実に出るため、格差について書くことは容易い。200字程度の要約であれば、結論・根拠・具体例の順番で書くのが良いだろう。
問2……
基本的に、同じ視点で分析しているにも関わらず異なる結論になる場合には、共通の前提・共通の理想を持ちつつも、問題解決のプロセスが異なるケースが多いので、それぞれの共通の前提・共通の理想と、それぞれが採用している思考プロセスの違いが明確に分かるように要約を構成すると良い。5STEPsの議論の整理の構成をそのまま使うような形になる。
問3……
(1)国際比較(2)職業の世代間移動(3)高齢化という三つの視点で見た時の変化をすべて予想しなさいとあるが、基本的には(3)高齢化を軸に書いて、その後(1)国際比較(2)職業の世代間移動の視点から考えられることを書くと良い。基本的には、
議論の整理……2020年の日本の格差の状況について(ここに国際比較や世代間移動の話も入れる)
問題発見……2020年の日本の格差の状況を可視化する上で、どのような調査が必要か?(なぜ可視化できないか?、ここで特に高齢者の貧困に焦点を絞る)
論証……なぜ可視化できないか?の論証
解決策or結論……可視化するための解決策or結論
解決策or結論の吟味……他の調査方法と比較した場合の吟味
という構成で書くと良い。
[模範解答]
問1(60/200)
資料5(PREP法)(30/60)
結論・根拠……
10点満点、結論5点、根拠5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
所得分配の平等・不平等を論じる際には、家計の構成人数によって調整を加える必要がある。なぜなら、扶養家族が多い家計と少ない家計では、一人あたりの所得、あるいは一人あたりの消費額が異なるためだ。このことが、豊かさの程度、すなわち厚生水準にも影響を及ぼす。
具体例……
具体例10点満点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
たとえば、1960年台には世帯あたり人数は4人を超えていたが、現在では世帯あたり人数は3.72人であり、家族構成人員は相当減少していることがわかる。この要因としては、単身者の増加、とくに高齢単身者の増加がある。
そこから導き出される結論……
結論10点満点、原則5点、例外5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
こうした世帯人数の減少は、本来一人あたりの収入を増加される効果があるが、高齢単身者については年金受給額の低下などで一人あたりの収入を減少させる効果がある。
資料6(PREP法)(30/60)
結論・根拠……
結論10点、根拠10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
日本におけるジニ係数の上昇は、人口構成の変化によるものであると考えられる。なぜなら、日本では高齢化が進んでいるからだ。一般に高齢者になればなるほどジニ係数は高くなる。たとえ年齢間格差および同一年令グループ内の所得分配が同一であっても、人口構成の変化によって所得分配が悪化したように見える可能性はある。
具体例……
具体例、1例で5点、2例で5×2=10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
たとえば、高齢者になればなるほど所得分配の格差が大きくなる理由としては、高齢者になればなるほどそれまでの勤労の成果が如実に出ることに加えて、相続資産額の格差によるものも大きい。
結論……
この結論は繰り返しなので合ってもなくても良い
そうした要因から、年齢間格差および同一年令グループ内の所得分配が同一であっても、格差が拡大しているように見えることは十分に考えられる。
問2(40/200)
共通の前提……
共通の前提4点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
資料5・資料6ともに、高齢化による人口構成の変化がジニ係数の上昇をもたらしているという立場を取る。
それぞれの相違点……
両方の要因で各9点×2、分析の違いが生じる要因で各9点×2、合計36点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
一方、資料5ではその要因を単身高齢者の増加による年金受給額の減少としているが、資料6では相続資産の差異による格差の拡大としている。こうした分析の違いが生じる要因としては、資料5は給料所得などのフローを中心に分析しているのに対し、資料6は相続資産から得られる収入などのストックを意識して分析しているためである。
問3(100/200)
議論の整理……2020年の日本の格差の状況について(ここに国際比較や世代間移動の話も入れる)
20点満点、予想10点、理由10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
2020年の日本の格差の状況については、再配分後も含めて、現在よりも深刻にジニ係数が上昇すると考えられる。なぜなら、日本の社会福祉が国際比較上も高収入の高齢者にも手厚い再配分をしているという顕著な特徴を持つ上、経済格差の拡大による教育格差の拡大などで職業の世代間移動も難しくなると考えられるためだ。
問題発見……2020年の日本の格差の状況を可視化する上で、どのような調査が必要か?(なぜ可視化できないか?、ここで特に高齢者の貧困に焦点を絞る)
20点満点、なぜ可視化出来ないかを問題提起にしていればその時点で10点、新規性5点、着眼点の緻密さがあれば5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
こうした日本の格差問題を考える上で、特に高齢者間の格差について正確な調査を行うことの重要性である。高齢者間の格差について調査を行うことが難しい背景としては、高齢者間の格差を生み出すのは、所得格差よりむしろ資産格差、もっといえば資産格差が生み出す実質的可処分所得格差にあるためである。
論証……なぜ可視化できないか?の論証
20点満点、論証がなされていれば10点、新規性があれば5点、緻密性(複数の根拠で結論を支える、深堀りするなど)があれば5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
こうした資産格差が生み出す格差について、所得格差を捕捉する場合よりも調査が難しい理由としては、資産については所得よりも定量的な比較が難しいためである。たとえば、資産価値がほとんどない不動産であっても、実際そこに居住している場合は可処分所得は増える。この可処分所得の格差こそが、実質的な高齢者間の格差を定量化するためには極めて重要になる。また、食料の調達についても、農家などであれば米や野菜などは自前で調達できるため、可処分所得は増える。こうした可処分所得に焦点を当てた分析こそが、高齢者間の格差を考える上では重要になる。
解決策or結論……可視化するための解決策or結論
20点満点、方法とそのための手段が書かれていれば各5点、それぞれについて新規性があれば各2点、実効性があれば各1点、緻密性があれば各2点加点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
こうした実質的可処分所得を捕捉するためには、まず収入と支出をすべてビックデーターとして捕捉した上で、それぞれの個々人の実質的可処分所得を収集する必要がある。その上で、一年単位でそれぞれの個々人の実質的可処分所得を集計し、その所得格差についてジニ係数としてまとめることで、高齢者の真の格差を把握することができるだろう。
解決策or結論の吟味……他の調査方法と比較した場合の吟味
20点満点、他説との比較10点、利害関係者検討10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
ほかにも、資産額の格差で高齢者間の格差を評価する方法もあるが、資産額のみの評価ではかならずしも高齢者の生活実感に則した格差の把握はできない。やはり高齢者の生活実感に則した形で高齢者感の格差を把握するためには、可処分所得の格差に焦点を絞ったジニ係数の把握こそが必要だろう。









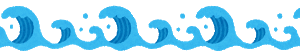



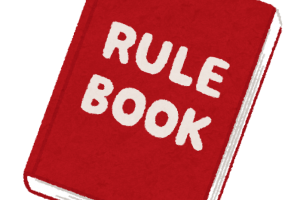

コメントを残す