問題
次の、詩人・石原吉郎(1915年[大正4年]–1977年[昭和52年])による論考「ある<共生>の経験から」を読んで、後の問いに答えなさい。
<共生>という営みが、広く自然界で行なわれていることはよく知られている。たとえば、ある種のイソギンチャクはかならず一定のヤドカリの殻の上にその根をおろす。一般に共生とは二つの生物がたがいに密着して生活し、その結果として相互のあいだで利害を共にしている場合を称しており、多くのばあい、それがなければ生活に困難をきたし、はなはだしいときは生存が不可能になる。私が関心をもつのは、たとえばある種の共生が、一体どういうかたちで発生したのかということである。たぶんそれは偶然な、便宜的なかたちではじまったのではなく、そうしなければ生きて行けない瀬戸ぎわに追いつめられて、せっぱつまったかたちではじまったのだろう。しかし、いったんはじまってしまえば、それは、それ以上考えようのないほど強固なかたちで持続するほかに、仕方のないものになる。これはもう生活の智恵というようなものではない。連帯のなかの孤独についての、すさまじい比喩である。
私がこう思うのは、私自身に奇妙な<共生>の経験があるからである。
私は、昭和二十年敗戦の冬、北満(ア)でソ連軍に抑留され、翌二十一年初めソ連領中央アジヤ(イ)の一収容所へ送られた。この昭和二十一年から二十二年へかけての一年は、ソ連の強制収容所というものをまったく知らない私たちにとっては、未曾有(ウ)の経験であった。入所一年目に私たちが経験しなければならなかったかずかずの苦痛のうち最大のものは徹底した飢えと、しばしば夜間におよぶ苛酷な労働である。当時ウクライナ方面で起った飢饉のため、全般的に食糧事情が悪化しており、まして私たちは一般捕虜とちがい、大部分が反ソ行為の容疑者から成る民間抑留者の集団であったため、食糧にたいする顧慮が十分行なわれなかったとしても不思議ではない。加えて、どこの収容所にも見られる食糧の横流しが、ここでは収容所長の手で組織的に行なわれ、これが給養水準の低下に拍車をかけた。
このため入所後半年ほどで、私たちのあいだには、はやくも栄養失調の徴候があらわれはじめた。
こういった事情のもとで、おそらくはこの収容所に独特の、一種の<共生>ともいうべき慣習がうまれ、またたくまに収容所全体に普及した。<共生>が余儀なくされた動機には、収容所自体の管理態勢の不備のほかに、一人ではとても生きて行けないという抑留者自身の自覚があったと考えてよい。まず、この収容所は民間抑留者が主体であって、大部分が食器を携行して入ソした一般捕虜の収容所にくらべて、極端に食器がすくない。したがって食事は、いくつかの作業班をひとまとめにして、順ぐりに行なわれることになるが、そのさい食器(旧日本軍の飯盒(エ))を最大限に活用するために、二人分を一つの食器に入れて渡す。これを受けとるために、抑留者は止むをえず、二人ずつ組むことになったが、
私たちはこれを<食罐組(オ)>と読んだ。これがいわば、この収容所における、<共生>のはじまりであるが、爾後(カ)この共生は収容所生活のあらゆる面に随伴することになった。
食罐組をつくるばあい、多少とも親しい者と組むのが人情であるが、結局、親しい者と組んでも嫌いなものと組んでも、おなじことだということが、やがてわかった。というのは、食糧の絶対的な不足のものでは、食罐組の存在は、おそかれはやかれ相互間の不信を拡大させる結果にしかならなかったからである。
一つの食器を二人でつつきあうのは、はたから見ればなんでもない風景だが、当時の私たちの這いまわるような飢えが想像できるなら、この食罐組がどんなにはげしい神経の消耗であるかが理解できるだろう。私たちはほとんど奪いあわんばかりのいきおいで、飯盒の三分の一にも満たぬ粟粥を、あっというまに食い終ってしまうのである。結局、こういう状態がながく続けば、腕ずくの争いにまで到りかねないことを予感した私たちは、できるだけ公平な食事がとれるような方法を考えるようになった。まず、両方が厳密に同じ寸法の匙を手に入れ、交互にひと匙ずつ食べる。しかしこの方法も、おなじ大きさの匙を二本手に入れることがほとんど不可能であり、相手の匙のすくい加減を監視するわずらわいさもあって、あまり長つづきしなかった。つぎに考えられたのは、飯盒の中央へ板または金属の<仕切り>を立てて、内容を折半する方法である。しかしこの方法も、飯盒の内容が均質の粥類のときはいいが、豆類などのスープの時は、底に沈んだ豆を公平に両分できず、仕切りのすきまから水分が相手の方へ逃げるおそれもあって、間も無くすたった。さいごに考えついたのは、罐詰の空罐を二つ用意して、飯盒からべつべつに盛り分ける方法である。さいわいなことに、ソ連の罐詰の企画は二、三種類しかないので、寸法のそろった空罐を作業現場などからいくらでも拾ってくることができる。分配は食罐組の一人が、多くのばあい一日交代で行なったが、相手に対する警戒心が強い組では、ほとんど一回ごとに交代した。この食事の分配というのが大へんな仕事で、やわらかい粥のばあいはそのまま両方の空罐に流しこんで、その水準を平均すればいいが、粥が固めのばあいは、押しこみ方によって粥の密度にいくらでも差が出来る。したがって、分配のあいだじゅう、相手はまたたきもせずに、一方の手許を凝視していなければならない。さらに、豆類のスープの分配に到っては、それこそ大騒動で、まず水分だけを両方に分けて平均したのち、ひと匙ずつ豆をすくっては交互に空罐に入れなければならない。分配が行なわれているあいだ、相手は一言も発せず分配者の手許をにらみつけているので、はた目には、この二人が互いに憎みあっているとしか思えないほどである。こうして長い時間をかけて分配を終ると、つぎにどっちの罐を取るかという問題がのこる。これにもいろいろな方法があるが、もっとも広く行なわれたやり方では、まず分配者が相手にうしろを向かせる。そして、一方の罐に匙を入れておいて、匙のはいった方は誰が取るかとたずねる。相手はこれにたいして「おれ」とか「あんた」とか答えて、罐の所属がきまるのである。このばあい、相手は答えたらすぐうしろをふり向かなくてはならない。でないと、分配者が相手の答に応じて、すばやく匙を置きかえるかも知れないからである。
食事の分配が終ったあとの大きな安堵感は、実際に経験したものでなければわからない。この瞬間に、私たちのあいだの敵意や警戒心は、まるで嘘のように消え去り、ほとんど無我に近い恍惚状態がやってくる。もはやそこにあるものは、相手にたいする完全な無関心であり、世界のもっともよろこばしい中心に自分がいるような錯覚である。私たちは完全に相手を黙殺したまま、「一人だけの」食事を終るのである。このようなすさまじい食事が日に三度、かならず一定の時刻に行なわれるのだ。
共生の目的は他にもある。たとえば作業のときである。私たちの労働は土工が主体であったが、土工にあっては工具(スコップ、つるはし)の良否が徹底してものをいう。それは一日の体力の消耗に、直接結びつくからである。毎朝作業現場に到着するやいなや、私たちは争って工具倉庫へとびこむのだが、いちはやく目をつけた工具を完全に確保するためには、最小限二人の人間の結束が必要である。食事のときあれほど警戒しあった二人が、ここでは無言のまま結束する。
こうして私たちは、ただ自分ひとりの生命を維持するために、しばしば争い、結局それを維持するためには、相対するもう一つの生命の存在に、「耐え」なければならないという認識に徐々に到達する。これが私たちの<話合い>であり、民主主義であり、一旦成立すれば、これを守りとおすためには一歩も後退できない約束に変るのである。これは、いわば一種の掟であるが、立法者のいない掟がこれほど強固なものだとは、予想もしないことであった。せんじつめれば、立法者が必要なときには、もはや掟は弱体なのである。
私たちの間の共生は、こうしてさまざまな混乱や困惑をくり返しながら、徐々に制度化されて行った。それは、人間を憎みながら、なおこれと強引にかかわって行こうとする意志の定着化の過程である。(このような共生はほぼ三年にわたって継続した。三年後に、私は裁判を受けて、さらに悪い環境へ移された。)これらの過程を通じて、私たちは、もっとも近い者に最初の敵を発見するという発送を身につけた。たとえば、例の食事の分配を通じて、私たちをさいごまで支配したのは、人間に対する(自分自身を含めて)つよい不信感であって、ここでは、人間はすべて自分の生命に対する直接の脅威として立ちあらわれる。しかもこの不信感こそが、人間を共存させる強い紐帯(キ)であることを、
私たちはじつに長い期間を経てまなびとったのである。
強制収容所内での人間的憎悪のほとんどは、抑留者をこのような非人間的な状態へ拘禁しつづける収容所管理者へ直接向けられることなく(それはある期間、完全に潜伏し、潜在化する)、おなじ抑留者、それも身近にいる者に対しあらわに向けられるのが特徴である。それは、いわば一種の近親憎悪であり、無限に進行してとどまることを知らない自己嫌悪の裏がえしであり、さらには当然向けられるべき相手への、潜在化した憎悪の代償行為だといってよいでしょう。
こうした認識を前提として成立する結束は、お互いがお互いの生命の直接の侵犯者であることを確認しあったうえでの連帯であり、ゆるすべからずものを許したという、苦い悔恨の上に成立する連帯である。ここには、人間のあいだの安易な、直接の理解はない。なにもかもお互いにわかってしまっているそのうえで、かたい沈黙のうちに成立する連帯である。この連帯のなかでは、けっして相手に言ってはならぬ言葉がある。言わなくても相手は、こちら側の非難をはっきり知っている。それは同時に、相手の側からの非難であり、しかも互いに相殺されることなく持続する憎悪なのだ。そして、その憎悪すらも承認しあったうえでの連帯なのだ。この連帯は、考えられないほどの強固なかたちで、継続しうるかぎり継続する。
これがいわば、孤独というものの真のすがたである。孤独とは、けっして単独な状態ではない。孤独は、のがれがたく連帯のなかにはらまれている。そして、このような孤独にあえて立ち返る勇気をもたぬかぎり、いかなる連帯も出発しないのである。無傷な、よろこばしい連帯というものはこの世界に存在しない。
この連帯は、べつの条件のもとでは、ふたたび解体するであろう。そして、潮に引きのこされるように、単独な個人がそのあとに残り、連帯へのながい、執拗な模索がおなじようにはじまるであろう。こうして、さいげんもなくくり返される連帯と解体の反復のなかで、つねに変らず存続するものは一人の人間の孤独であり、この孤独が軸となることによって、はじめてこれらのいたましい反復のうえに、一つの秩序が存在することを信ずることができるようになるのである。
一日の労働ののち、食事に次いでもっともよろこばしい睡眠の時間がやってくる。だが、この睡眠の時間にあっても、<共生>は継続する。とくに収容所生活の最初の一年、毛布一枚の寝具しか渡されなかった私たちは、食罐組どうしで二枚の毛布を共有にし、一枚を床に敷き、一枚を上に掛けて、かたく背なかを押しつけあってねむるほかなかった。とぼしい体温の消耗を防ぐための、これが唯一つの方法であった。いま私に、骨ばった背を押しつけているこの男は、たぶん明日、私の生命のなにがしかをくいちぎろうとするだろう。だが、すくなくともいまは、暗黙の了解のなかで、お互いの生命をあたためあわなければならないのだ。それが約束なのだから。そしておなじ瞬間に、相手も、まさにおなじことを考えているにちがいないのである。
昭和二十三年夏、私たち抑留者は、それぞれ運命を異にするいくつかの集団に分割されて出発した。私の食罐組のさいごの相手は、その時、別の集団に編入されて私の目の前から姿を消したが、その後、私が彼を憶い出すことはほとんどなかった。
(石原吉郎著「ある<共生>の経験から」【石原吉郎詩文集】講談社文芸文庫, 2005年, 89-97頁。初出は雑誌『思想の科学』1969年3月。某店は原文の通り。ルビは出題者による。)
注
- 北満:旧「満州」北部。
- 中央アジヤ:中央アジアに同じ。
- 未曾有:いまだ嘗て起こったことがないこと(『広辞苑 第六版』岩波書店)。
- 飯盒:アルミニウムなどで作った底の深い炊飯兼用の弁当箱。軍隊や登山などで用いる(『広辞苑 第六版』)
- 食罐:食缶に同じ。
- 爾後:それ以後。
- 紐帯:二つのものを結びつける役割をなしているもの。社会の構成員を結びつけて、社会をつくりあげている条件(『広辞苑 第六版』)。
-
本文の要旨を300字程度で記しなさい。
議論の整理→共生から連帯、秩序に至る流れの整理
問題発見→不要
論証→不要
解決策or結論→不要
解決策or結論の吟味→不要
共生が発生するのは、偶然ではなく、そうしなければ生きていけない瀬戸際に追い詰められた結果だと考える。筆者はそのことを収容所での生活で経験した。過酷な環境において、自分の生命を維持するためには、相対するもう一つの生命に耐えなければならないと認識するようになる。さらに、そのような不信感や憎悪、自己嫌悪をも含んだ上での生まれた連帯は強固なかたちで持続するが、同時に孤独でもある。孤独とは決して単独な状態ではなく、連帯のなかにはらまれている。また、この連帯は別の条件では解体し、単純な個人から新たな連帯が生まれる。常に変わらずあるものは一人の人間の孤独であり、このような連帯と解体の繰り返しから秩序が存在する。
(302)
-
あなたが今日の世界、社会、文化で想到する<共生>のあり方を、筆者の議論がもつ可能性や限界を考えながら、具体的事例に即して600字程度で述べなさい。
議論の整理→題材をどうするか定義する
今回、「夫婦」という共生のあり方について議論を進める。夫婦とは、2人の人間が婚姻を結び、一つの世帯を作るパートナーとなる関係である。夫婦は、収入面や家事に関する秩序を作り上げる点で共生していく。お互いに役割を分担し連携をとりながら、ひとつの世帯という秩序を生み出すのである。
問題発見→定義の中での問題について論述
まず、収入や家事を分担することを考えると、その分配が重要だ。その過程で、どちらか一方に負担が偏ると不信感が生まれる。また、それぞれの育ってきた文化の違いにより、ストレスが生じ得るだろう。時には耐えることも必要かもしれない。相手の存在を利用するのではなく、お互いにわかりやすく貢献しながら、世帯という秩序を作り出す。そして、ライフイベントに応じて秩序の形を変えながら、生涯を共にする関係が夫婦だと考える。
論証→筆者の説との比較
一方、絶対に相手といなければ、という力学が働かない点は筆者の主張と異なる。共生せずとも命に危険があるわけではないので、いざとなったら離婚という手段をとることもできる。しかし、夫婦になるまでの過程で信頼や愛情の積み重ねがあったならば、その結末を安易に選ぶのは悲しいことである。
解決策or結論→結論
結論、夫婦関係における共生とは、一つの世帯を作るため、自分と相手という別個の人間同士があたりまえを重ね合わせることだと考える。時には耐えたり不信感を感じながら、相互に理解をする。その過程で、それぞれ夫婦にとっての秩序が生まれてくるのではないだろうか。
解決策or結論の吟味→不要
(計600字)






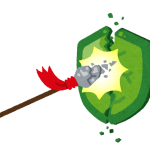

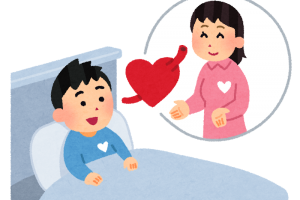



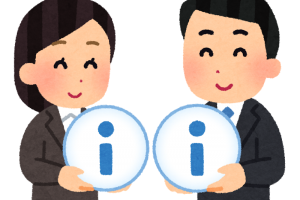

コメントを残す