次の文章を読んで、後の設問に答えなさい。
先頃、静岡の新聞社から「静岡の中学校では最近、短い時間の朝礼でも子どもたちを体育の時の三角すわりで坐らせているところが増えているが、これに対してどう考えるか」という質問を受けた。朝礼は立って行うものだという前提は、もはや成り立っていない。生徒を座らせるのは、そうしなければ倒れる生徒が出てくるからである。しかも、いきなりバタッと倒れるケースがかなりあるという。
長時間立っていることが出来ないだけでなく、長時間歩き続けることもまた苦手になってきている。遠足でも長い距離を歩き通すことが出来ない子どもが多いために、距離を短くしたり、そもそも歩かずにバスを利用する場合も少なくない。
学力低下が最近問題になってきているが、よりはっきりと低下の傾向を示しているのは、体力である。文部省による調査報告書(一九九八年)によれば、たとえば背筋力は、確実に低下し続けている。背筋力というと、背中の力を測っているようだが、実際には、大臀筋をはじめとした足腰の力が測定されている。ここで必要とされている筋肉は、直立姿勢を保つのに必要な筋肉である。したがってこの低下傾向は、長時間の歩行や立位姿勢保持が困難になってきていることを裏付けるものだ。
子どもの体の危機に対して、早くから警鐘を鳴らしてきた正木健雄によれば、この背筋力の低下は「腰の力の衰退」であり、一週間に一回「綱引き大会」などを行うことによって、腰の力の低下をくい止めることができるということである。正木は、このほかに、子どもの体温が低くなったこと、土踏まずがうまくできにくくなったこと、自律神経系の働きが弱くなってきたことなどを、近年の子どもの変化としてあげている。
こうした体力低下の傾向は、確かに問題である。しかし、私が考えるところ、より深刻なのは、伝統的な身体文化の喪失ということである。文明生活が進展し、からだを日常生活の中で使う機会が減れば、当然体力は低下する。この体力低下をスポーツやウォーキングによって、意識的にくい止める工夫も先進国ほど進んでいる。からだをあまり使わなくてよい便利な生活が浸透しているのは、欧米諸国も同様であるにもかかわらず、彼らと比較して、日本人の立ち姿や座り姿における姿勢の悪さは、際立っている。
立つことや坐ることや歩くことは、人間にとって基本的なことではあるが、これらは文化的なものでもある。立ち方、座り方、歩き方は、民族や文化によってそのスタイルは異なっている。正坐を例に取れば、長時間の正坐に耐えることができるためには、文化的な習練が必要とされる。これは、畳の上の「坐の文化」が生みだした、文化としての生法である。立つ、坐る、歩くといった基本的なことにも、文化の型というものがある。この文化の型の土台を継承することによって、強靭で、効率のよい姿勢を「技」にすることができる。反対に身体文化の継承に失敗すれば、立・坐・歩の基本は崩れる。
かつての日本では、立つことは確かな技として共有されていた。幕末から明治初期にかけての写真を見ると、当時の日本人のからだにおいては、「技としての自然体」が成り立っていたことがわかる。大地を踏みしめ力強く下半身は安定し、中心軸はしっかりと通っていて、肩の力は抜けている。立っている姿からだけでも、存在感が伝わってくるのである。
立ち姿全体から生きている「張り」が発散されている。臍下丹田の位置に帯がキュッと締められ、存在感の中心が、その帯が結ばれた臍下丹田にあることが明確である。帯やはちまきによって、心身が引き締められている。この引き締まった張りのある明るさは、現代の大人の立ち姿からは失われてきているものである。
一九三七年から十年間日本に滞在したドイツ人哲学者デュルクハイムは、日本人の姿勢が精神的な意味合いを多く持っていることに感銘を受け、『肚 人間の重心』という本を著した。デュルクハイムは、写真に写るときの立ち姿について、ヨーロッパ人は、どちらかの足に重心をかけて、肩をあげて胸を張り、「立派な」ポーズを取るが、日本人は肩と腕の力を抜き、背筋を伸ばして股を広げて立ち、片方の足にだけ重心をかけることをしないと言っている。「中心をもたずに立っている人は、日本人にとっては頼もしく見えないのである。なぜならそういう人は心の軸をもたないからである」とデュルクハイムは言う。
下半身が充実し上半身の力が抜けた、「上虚下実」の自然体は、日本の基本的な身体文化であった。ヨーロッパ人と日本人がともに集まったパーティにおいて、ある日本人がデュルクハイムに、ここにいるヨーロッパ人は後ろから押されるとすぐ転ぶ姿勢をしているが、日本人の中には押してもバランスを崩す人はいないでしょうと言った。樹木の幹のような安定感と柔らかさをもって立つことは、武士やいわゆる教養のある階層の人々にとってだけでなく、様々な階層・職業の人々において共有されていた身体の文化であった。
言語に関わることは文化として認められやすいが、身体関係は文化として認知されにくい。たとえば丹田呼吸法は、身体文化の精髄であるが、学校カリキュラムに入れられてさえもいない。「蹲踞」という姿勢ができなくなっても、それを文化の喪失だとは一般の人は感じていない。「身体文化」という視座から歴史を振り返ったときに、この百年余りの間に失われた文化の大きさに私は衝撃を受ける。
数百年以上にわたって蓄積し、練り上げてきた伝統的な身体文化を、急速に失ってしまったことの重大な意味は、現在のところ明確に認識されているとは言いがたい。伝統的な身体文化を喪失する一方で、欧米的な生活様式に即した欧米流の身体文化を、技として身につけているというわけでもない。このどっちつかずの状態は、深刻な身体文化の貧しさを示すものである。
文化は、強い継承の意志を持たなければ自ずと衰退する。身体文化という視座を確立し、伝統的な身体文化の中から継承すべきものを絞り込んだ上で、現在の生活様式に即した身体文化を創り上げていくこと、これが緊急の課題である。
II
では、伝統的な身体文化とは何か。
伝統的な身体文化と聞けば、能や歌舞伎や剣道といったものを思い浮かべる。現在は「伝統文化の理解」ということが、教育の柱の一つとして言われはじめている。歌舞伎を、学校行事として観に行くところも多い。あるいは運動会で、ソーラン節や民舞を取り入れるのも、一種の流行になっている。こうしたものは確かに伝統的な文化の典型であるが、それらがジャンルや型として確立されているがために、日常生活との連続性を見出しにくいという弱点を持っている。
歌舞伎や能は、確かに伝統的な身体文化の代表である。しかし、そこでの身体文化は高度に様式化されているために、自分の日常生活における身体のあり方と地続きのものとして捉えられにくい。「ああ、これは歌舞伎だ」というように、くくられ整理されてしまいがちだ。能や歌舞伎における身体性や型は、伝統的な身体文化全体のいわば結晶である。その結晶を生みだしている母体は、日常的な身体性である。今教育において重要なことは、日常生活における身体のあり方を、文化として明確に捉え直し、継承するということではないか。
武道・芸道における特別な訓練をたとえ受けていなくても、かつては日常生活の中で十分に伝統的な身体文化は継承されていた。遊び、そうじ、風呂たき、食事、子守り、祭りの御興など、日常の諸活動において、身体は文化的に鍛錬されてきた。
その伝統的な身体文化の内実は、私が絞り込んだ概念でいえば、<腰肚文化>と<息の文化>である。
日本人は伝統的に、「腰」と「腹(肚)」を非常に重要視してきた。身体の中心をつくり、活動を安定させる基本が、腰の構えにあるとされた。多くの職人仕事で、腰はキーワードとなっていた。「腰を据える」「腰を決める」「腰くだけ」などの腰にまつわる「からだ言葉」は、数多い。それらは身体の構えの基本を表現していると同時に、心の構えも教育する機能を持っている。身体の中心(あるいは中心軸)をつくることが、精神の中心をつくることに直接結びつけられて考えられていたのである。
この事情は、「腹(肚)」に関しても同様である。「肝を据える」「肝が大きい」などといった表現は、身体と精神が重なり合う構えの次元の言葉である。という漢字表記は、とくに精神的意味を含んだものだが、現在は用いられることはほとんどない。この腹という概念は、人間の「器」を表すものでもある。
身体論的に言えば、このは、丹田呼吸法と結びついている。丹田呼吸法は、吐く息を長くする深い腹式の呼吸法である。戦前の人々にとっては、「臍下丹田」という言葉は、日常的に用いられる言葉であった。大正時代に、岡田式呼吸静坐法をはじめとした呼吸法ブームがあったことも、この概念の普及には役立った。しかし、敗戦とともに丹田呼吸法や臍下丹田は大した根拠もなく古くさいものとして廃れていった。現在は、ほぼ死語となっている。
臍下丹田に中心をおく「自然体」は、ヨガ、道教、禅など様々な東洋的身体技法の伝統を引き継いだものである。自然体は文化であり、習練によって獲得される一つの「技」である。「上虚下実」の自然体を技として身につけていることによって、様々な活動が質的に向上する。無駄な力が抜け、柔軟にかつ強靭に物事に対処できる基本が、自然体という構えである。この自然体という技は、<腰肚文化>と、丹田呼吸法に代表される<息の文化>の結晶である。
Ⅳ
<腰肚文化>やく息の文化>といった概念自体はなかったにせよ、かってはこの二つの身体文化は常識であり、明確に重要視され継承されてきた。この伝統的な身体文化の継承を典型的に見せてくれるのは、幸田露伴−幸田文−青木玉の三代である。幸田露伴は大文学者であると同時に、身体文化の巨匠でもあった。娘の文に、自ら雑巾がけや薪割りといった日常生活における身体文化を厳しく仕込んでいる。その身体文化の伝承の模様は、幸田文の『父・こんなこと』に詳しい。
露伴は、家事一切すべての身体の用い方を自らやってみせる。露伴の教育方法は、まずやらせる、次に手本をやってみせる。そしてもう一度やらせる、というものであった。このやり方は、学ぶ側の<(技を)まねる・ぬすむ力>を養う教育方法である。文によれば、露伴の雑巾がけは、身のこなしに折り目、決まりがあり、芝居の動作のようであったという。雑巾がけの基本は、足腰の安定である。
私のとりわけ好きな文章は「なた」というものである。露伴は、なたでの薪割りを文に仕込む。文がなたを薪に食い込ませ、二度三度コツコツとたたいて割っているのに対して、「構えが足りない」と言い、次のように具体的な指示を与える。「二度こつんとやる気じゃだめだ、からだごとかかれ、横隔膜をさげてやれ。手のさきは柔かく楽にしとけ。腰はくだけるな。木の日、節のありどころをよく見ろ。」
「横隔膜をさげてやれ」という指示は、息を溜める丹田呼吸法の指示のことである。「腰はくだけるな」というのであるから、まさにこれは、腰肚文化の精髄を、薪割りを通して伝えようとしている。なたを振り上げた腰の構えが決まっていないと、「ちょいと蹴飛ばされるとひっくりけえっちまう」と叱咤される。ここで露伴は、薪割りという技を通して、全身の力を込める「渾身」という構えや、腰肚文化、息の文化といった身体文化を娘に継承させている。継承というよりも、たたき込んでいると言った方が適切なほどの強烈さで、文化の伝承は身体を通して行われる。
この短文は、伝統的な身体=精神文化を凝縮した名文であるので、私は時々小学校でこれをテキストにして授業を行っている。渾身という文字を染め抜いたTシャツを用意していったり、実際に薪を割って見せたり、名刺で割り箸を断ち切ったり、二分間の丹田呼吸法を合わせて行うことによって、相当盛り上がる。
幸田家の面白いところは、父に鍛えられている間は、その厳しさに抵抗していた文もまた、娘の玉には同じことをやっているというところである。青木玉は『小石川の家』の中でこう書いている。
「小学校の六年の時、恒例の書き初めにどうしたわけか、母は改めてお稽古をしなさいと言い出した。書き初めは半紙三枚を縦長にしたくらいの大きさになるから畳に紙を置いて左手を支えにして習う。勢い重心が前へかかり腰が浮く。筆を下そうとした時、いきなり後ろから蹴とばされた。体が飛んでおでこが畳にこすれ、そこいらじゅう墨だらけになった。うつむいて座り直した私に、『わかった』と母は切り込んで来た。何か言わねばならない、あの、あの、とあとがつづかない。『ごめんなさい。わかりません』『腰が決らないで字は書けないと、あれ程いったのに、後ろから蹴とばしたくなるような恰好で習字が出来るわけがない。物を習う気構えが出来てない、あんたという人は−−』あとは年末大棚ざらえの小言の山、夜店のたたきバナナである。『ひっぱたかれて痛いとあんたは泣くけど、母さんの手も痛いのよ』痛いも痛かったがこれは利いた。」
腰がきまらないことを何よりも嫌い、蹴飛ばしてでも構えを鍛える。露伴も文も、これが身体の構えだけでなく、精神の構えにも通じているということを深く認識していたからこそ、徹底してたたき込んだのであろう。幸田家の場合は、一般の家とはもちろんケースが異なる。しかし普通の家でも、日常の様々な機会に、腰肚文化と息の文化は、教育され伝承されていた。食事の時や正式の場における正座の教育も、その一つである。
現在は生活様式も大きく変化してきているので、雑巾がけや薪割りといった活動が日常から姿を消しつつある。生活という文脈においては、これは致し方のないことであるが、教育という文脈においては、こうした身体文化を意識的に保存継承するということも十分に価値のあることである。古いものを強制するということではなく、身体の技を継承するという意識が重要である。
私が腰肚文化や息の文化といったことを重要視するのは、それが自己の「中心感覚」や「存在感」、あるいは「他者との間合い」といった感覚と深く結びついているからである。自分自身の存在を希薄なものに感じたり、自分に中心がないように感じられれば、自己肯定感もまた薄れる。自分自身の身体の内側に中心を感じることができれば、自分の存在に対する信頼感や肯定感は強化される。
臍下丹田に自分の中心があるように感じる感覚自体も、習練によって得られる一つの技である。反復して臍下丹田に意識を集めることによって、その感覚自体が習慣になってくる。この中心感覚が技化されることによって、自己のよりどころが生まれる。自分に対する信頼感が増すことによって、他者に対しての余裕も生まれてくる。自己の感覚が希薄であればあるほど、他者を受け入れにくくなる。伝統的な身体文化は、自己形成のプロセスにとって非常に重要な役割を果たしていたのである。
Ⅳ
こうした身体=精神文化は、親から子への躾けという形や、職人仕事における訓練などの教育的営為においてなされていただけではない。忘れてならないのは、かつての子どもの遊びに含まれていた総合的教育機能である。
かつての遊びは、身体全体を使うものが多くを占めていた。ゴムとびやおしくらまんじゅう、相撲やチャンバラ、鬼ごっこや馬とびなど、現在から見るとすべて体育のカリキュラムにしても良いようなものばかりである。こうした日常的な遊びの中で、足腰の強さを中心として全身が鍛えられた。かつての遊びは、身体全体の力強さやねばり強さを試し合い、鍛え合う要素を多く持っていた。
試され鍛えられたのは、身体ばかりではなく、勇気や我慢強さといったものも同時に鍛えられた。たとえば、昭和三十年代くらいまでは、男の子はよく塀に登っていた。その塀の上で話をしたりする。高い塀に登るための、力と技がまず試された。登れなければ話に加わりにくい。粘り強くチャレンジする必要があった。その高い塀から飛び降りることは、足腰の強さを要求し、それと同時に勇気を試すものでもあった。
また、ある程度の幅のある川やドブを飛び越えることも、遊びであると同時に鍛錬であった。私自身の経験でも、高い塀から無理して飛び降りたときの足の底からのしびれの感覚や、家の前の幅広のドブを飛び越えようとして失敗し、落ちたときに全身に染みついたドブの匂いなどが、今でも蘇ってくる。
相撲や馬乗りといった遊びは、明確に足腰の強さを試し合う遊びであった。前の子の股に頭をつっこんで馬をつなげ、そこへ相手方のチームがどんどん乗ってきて揺さぶってつぶすというのが、馬乗りである。私は小学校時代に、男女混合で遊びとしてやっていた。馬の弱いところは、強い子どもが補うようにして、馬がつぶれないように工夫する。
この激しい遊びは、からだの強さを試し合うだけでなく、体で触れ合いぶつかり合うタフさを育てるものでもあった。現在は、この馬乗りは、全くと言っていいほど行われていない。小学校の先生によれば、そもそも人の股に頭をつっこむということ自体が苦手なのだそうだ。しかも、男女が交じった形で、それを行うというのは難しいという。
息をぐっと胱に溜めて、自分の上に乗った相手の揺さぶりをこらえる。一人でこらえるのではなく、皆で息を合わせてこらえるのである。「息を溜める」ことと、「息を合わせる」こと。この二つの重要な息の技が、この遊びの中では自然と鍛えられていたのである。この遊びが日常から消えていったことによって、身体文化を伝承する一つの重要なカリキュラムが消えたということになる。
かつての遊びにおいては、子どもたちは一日に何度も息を切らし汗をかいた。自分の身体の全エネルギーを使い果たす毎日の過ごし方が、子どもの心身にとっては、測りがたい重大な意味を持っている。
この二十年ほどで、子どもの遊びの世界、特に男の子の遊びは激変した。外遊びが、極端に減ったのである。一日のうちで息を切らしたり、汗をかいたりすることが全くない過ごし方をする子どもが圧倒的に増えた。子ども同士が集まって野球をしたりすることも少なくなり、遊びの中心は室内でのテレビゲームに完全に移行した。身体文化という視座から見たときに、男の子のこの遊びの変化は、看過できない重大な意味を持っている。
相撲やチャンバラ遊びや鬼ごっこといったものは、室町時代や江戸時代から連綿として続いてきた遊びである。明治維新や敗戦、昭和の高度経済成長といった生活様式の激変にもかかわらず、子どもの世界では、数百年以上続いてきた伝統的な遊びが日常の遊びとして維持されてきたのである。
しかし、それが一九八〇年代のテレビゲームの普及により、絶滅状態にまで追い込まれている。これは単なる流行の問題ではない。意識的に臨まなければ取り返すことの難しい身体文化の喪失である。かつての遊びは、身体の中心感覚を鍛え、他者とのコミュニケーション力を鍛える機能を果たしていた。これらはひっくるめて自己形成のプロセスである。
コミュニケーションの基本は、身体と身体の触れ合いである。そこから他者に対する信頼感や距離感といったものを学んでいく。たとえば、相撲を何度も何度も取れば、他人のからだと自分のからだの触れあう感覚が蓄積されていく。他者と肌を触れ合わすことが苦にならなくなるということは、他者への基本的信頼が増したということである。これが大人になってからの通常のコミュニケーション力の基礎、土台となる。自己と他者に対する信頼感を、かつての遊びは育てる機能を担っていたのである。
この身体を使った遊びの衰退に関しては、伝統工芸の保存といったものとは区別して考えられる必要がある。身体全体を使ったかつての遊びは、日常の大半を占めていた活動であり、なおかつ自己形成に大きく関わっていた問題だからである。歌舞伎や伝統工芸といったものは、もちろん保存継承がされるべきものである。しかし現在、より重要なのは、自己形成に関わっていた日常的な身体文化そのものの価値である。数百年以上にわたって継承されてきた日常における身体文化が、数十年のうちに急激に喪失されたことの意味は深刻である。二十一世紀を迎えた現在において、身体文化に対して明確な意識をもって臨む必要がある。そのことが、現在問題になっている様々な社会問題に対する対処法の根幹をなすと考える。
(斎藤 孝「子供のカラダは崩れている」による)
問1.
本文で述べられている「上虚下実」とは何か、100字以内で説明しなさい。
議論の整理→不要
問題発見→これまでのデータを整理
論証→不要
解決策or結論→不要
解決策or結論の吟味→不要
下半身で力強く踏みしめ上半身からは力を抜いた、中心線がしっかりした佇まいのことである。かつての日本では基本的な身体文化として自然に根付いていた。また、立ち方だけではなく自己のありかたも同時に指す。
問2.
筆者が述べている「日本における伝統的な身体文化」とは何か、200字以内で説明しなさい。
議論の整理→筆者の言う「伝統的な身体文化」に関する記述を流れに沿ってまとめる
問題発見→不要
論証→不要
解決策or結論→不要
解決策or結論の吟味→不要
日本における伝統的な身体文化とは、<腰肚文化>と<息の文化>である。具体例として、「腰」や「腹」を含む様々な「からだ言葉」や、丹田呼吸法がある。これらは日本人の生活様式に密着しており、明確に重要視され継承されてきた文化である。この修練を通して身体の中心軸をつくることができ、それは精神の中心をつくることに直接結びつく。そのため、身体文化が自己形成のプロセスにとって非常に重要な役割を果たしている。
問3.
日本における伝統的な身体文化と自己形成との関係について、筆者の論点を踏まえながら、あなたの考えを700字以内で述べなさい。
議論の整理→筆者の意見の整理
筆者は身体文化の継承を通して子どもの自己形成が成されるが、近年その文化が急速に失われていると主張している。
問題発見→自分の考え
私も筆者と同様に、伝統的な身体文化から得られる自己信頼感は間違いなくあると考える。また、その文化が失われることが、深刻な社会問題の根幹を成していることも納得である。しかし、身体文化だけが自己形成のプロセスに必要だとは言い難い。逆に、テレビゲーム文化を通して生まれる自己形成もあるのではないだろうか。
論証→その背景を推察
身体文化は、体格やもともとの体力など、生まれ持った性質に依存する。なおかつ、その優劣が一目でわかりやすい。概して、身体が大きく体力がある子どもが目立ち、逆に身体が小さく体力がない子どもは集団の中で目立ちにくくなる。自分と他人の差を敏感に認識しやすい時期に、身体だけに依存する自己形成プロセスを踏むのは、劣等感を生むことにもつながると考える。
一方、テレビゲームの場合、体格や体力以外に知力やテクニックでの活躍が可能である。自己のよりどころは、自分の強みを見つけて自分に対する自信を持つことから生まれる。身体文化だけに囚われることは、幅広い分野の「強み」を見つけるきっかけの損失にもなり得るだろう。
解決策or結論→問題の解決策or結論を提示
以上より、身体文化の継承による自己形成も重要だが、時代の変化によって生まれた新しい文化を通じた自己形成にも価値があると考える。
解決策or結論の吟味→筆者の意見との照らし合わせ
単純に「テレビゲームをやめて外で遊びしなさい」というやり方が是ではない。また、逆に「外で遊ばなくてもいいから好きなだけゲームをやりなさい」というやり方も極端である。様々な文化を通して自分に対する信頼感を得て、余裕をもって他者を受けいれられる大人に成長することを期待する。
計699字







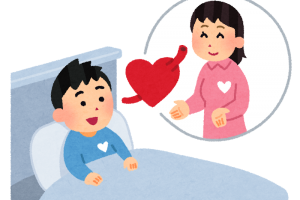


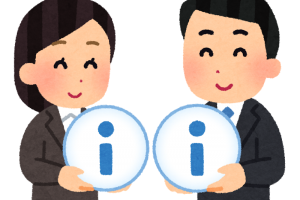



コメントを残す