次の文章を読んで、後の設問に答えなさい。
これまでの日本社会は、個の自立を阻んできた。だから、日本を変えるためには、「たくましく、しなやかな個」が求められる。だが、個の自立を阻む主な原因は、「場の和を第一に考える日本人の傾向」である。その結果が「先進国のなかでは貧富の差が少ない」社会を生み出す一方で、「個人の能力や創造力を存分に発揮させる場としてはむしろ足かせとなってきた」というのである。このような議論には、「和」を重視する日本人→「結果の平等」の強調→個の自立への足かせといった論理の展開が見てとれる。「『結果の平等』ばかりを問」うことで、「“出る杭”は打たれ続けてきた」。だから、結果の平等から機会の平等へと転換しなければならないというのである。
同様の認識は、「日本経済再生への戦略」の中でも、「21世紀の日本経済が活力を取り戻すためには、過度に結果の平等を重視する日本型の社会システムを変革し、個々人が創意工夫やチャレンジ精神を最大限に発揮できるような『健全で創造的な競争社会』に再構築する必要がある」といったように表現されている。
だが、このように指摘されている「結果の平等」とは、一体何を意味するのだろうか。「日本人のもつ絶対的とも言える平等感」とは何を指しているのか。
あとの議論を先取りすれば、「結果の平等」が足かせとなっているという見方を支えているのは、実はそれ自体が日本的な平等主義の考え方である。そして、この日本的な平等主義のとらえ方が一因となって、現在根深いところで生じている日本社会の変化から目がそれている。
この問題に答えるために、まずは、そもそも「結果の平等」という考え方が、どのような意味で、また、どのような歴史的文脈において登場したのかを探ってみよう。
II
一九六五年六月四日、前年に黒人差別の撤廃をめざした公民権法が成立したことを受け、アメリカの黒人の名門ハワード大学で、ときの大統領ジョンソンが「諸権利の達成のために」と題した演説を行った。「貧困との闘い」のいっそうの強化を提唱したのである。そして、この中で、「結果の平等」というまったく新しい平等の考え方が示されたのである。
長年にわたり、鎖につながれてきた人を解放し、競争のスタートラインに立たせ、「さあ、あなたは自由に他の人たちと競争ができる」と言い、それだけで自分は完全にフェアであると正しく信じようなどとすることはできない。機会の門戸を開くだけでは不十分である。われわれすべての市民は、この門戸を通り抜けるにたる能力を持たなければならない。これこそが、公民権のための闘いの、次なる、そしてより深遠な段階である。われわれは自由だけではなく機会を求める−たんなる法的な公正ではなく、人間的な能力を−、たんなる権利としての、理論としての平等ではなく、事実としての、結果としての平等を求めるのである。
「競争のスタートラインに立たせるだけでは、過去から蓄積された負の遺産(=差別や貧困)のハンディを取り除くことにはならない。だから、機会の平等だけでは不十分だというのである。これにつづく部分では、フェアな競争を可能にする条件の整備として、能力の発達の機会を保証しようという考え方が、「結果の平等」には含まれていたことが、さらに明確に示される。
二○○○万もの黒人たちに、多くのアメリカ人と同じように、学び成長し、働き、社会の一員となり、個人の幸福を追求することのできる能力を−肉体的にも精神的にも−伸ばすチャンスを与えることが課題である。
この目標のために、機会の均等は必要不可欠ではあるが、それだけでは十分ではない。どのような人種の男女も、さまざまな能力分布の幅(レンジ)は同じである。しかし、能力は生得的に決まるものではない。能力はどのような家族と生活をともにするか、どのような近隣に住んでいるか、どのような学校に行っているか、といった環境の豊かさや貧しさによって、能力が伸長されたり発達を阻まれたりするものである。
結果の平等とは、機会の平等の一層の徹底と、にもかかわらず、それでも公平な競争を阻む、歴史的に累積された負の遺産に目を向けて考え出された平等主義の考え方だったのである。だからこそ、この演説を受け、ヘッドスタートと呼ばれる補償教育(学校入学以前に教育上の文化的なハンディを克服しようとした)や、アファーマティブ・アクションと呼ばれる「結果の平等」政策(マイノリティに一定数の仕事や大学入学の枠をもうけた)が具体化していったのである。
この演説で表明された「結果の平等」という新たな平等の考え方に基礎を与えたのは、当時の労働次官補モイニハンが執筆した「モイニハン・レポート」であった。この内容を詳細に検討した黒崎勲によれば、「『結果の平等』の概念は(機会の)利用能力の平等とグループ間の平等という二つの要因から構成されるものであり、もとより、形式的な平等に対する実質的な平等として一般化されるべきものではない」。ここでいう、「(機会の)利用能力の平等」とは、同じスタートラインに立つために、それまでの負の遺産をできるだけ除去しようとする「人間的能力」の発達の保証=補償を指すことは明らかである。他方、「グループ間の平等」とは、一人ひとりの個人の違いを打ち消そうというのではなく、あくまでも、黒人など他の人種の人びとがグループとして、白人並みに機会の平等の恩恵に浴する条件の整備を求める考え方である。
Ⅲ
日本版の「結果の平等」と、アメリカのオリジナルは二つの点で大きく異なっている。ひとつには、後者の場合、機会の平等だけでは不十分であるといった認識から、結果の平等(=事実としての平等)を求めるといった方向で平等観の革新が起きた。ところが今日本では、結果の平等を脱却し、機会の平等へ向かうべきだという方向で平等観の変更が行われようとしている。図式的にいえば、〈アメリカ=機会の平等→結果の平等)に対し、〈日本=結果の平等→機会の平等〉という、まさに逆立ちした構図である。
二つ目の違いは、「グループ間の平等」という視点の有無である。アメリカの場合には、社会の構成員全員を等しく扱おうという平等がめざされたわけではなかった。マジョリティ・グループと同じ程度に機会の平等の恩恵にあずかることを求めた(だからこそ、不十分であったという批判が後に出てくる)。それに対し、グループ間の比較という理解ではなく、すべての個人を同じように処遇することに目を向けるのが、日本版「結果の平等」である。
このような違いに着目すると、日本における結果の平等という状況認識の特徴・問題点を、二つ指摘することができる。
第一に、日本版の結果の平等を下敷きにすれば、「事実としての(不)平等」には目が向きにくい。しかも、事実の検証抜きに、「横並び」といった日本文化論的な平等の理解をさしはさむことで、事実としての「結果の平等」が過度に実現しているといった誤解を与えてしまう。じっさい「二十一世紀日本の構想」の「日本人のもつ絶対的とも言える平等感」と深く関わるが、「『結果の平等』ばかりを問い、縦割り組織、横並び意識の中で、“出る杭”は打たれ続けてきた」という一文を正確に読めばわかるように、そこでは、事実としての「結果の平等」状態を問題にしているのではない。「『結果の平等』ばかりを問」う、そうした気分としての日本的な「平等感」が、「横並び意識」を生み、“出る杭”が打たれ続ける状況を作りだしてきた、と見ているのである。
ここでは、横並び意識といった心情をもとに、形式的な処遇の画一性を指して結果の平等状態とみなされている。それゆえ、結果の平等から機会の平等への転換が主張される中で、そもそも機会の平等がこれまでどれだけ実現してきたのかという事実に照らした検証も行われない。そこでの平等状態とは、アメリカ的な意味の平等からはほど遠いのである。
第二は、「グループ間の差異」という視点が欠けているために、すべての個人が能力や実績にかかわりなく同じ処遇を受けることを「結果の平等」として理解してしまう。それゆえ、結果の平等は機会の平等の不十分さを補うものであるという位置づけより、結果の平等が機会の平等を阻害していると見てしまう。これらの結果、日本版「結果の平等」は、事実としての不平等に目を向けることもなく、形式的な処遇の画一性を気にかけることに横滑りしている。
結果にいたるプロセスの形式的な画一性に目を向ける「横並び意識」とは、まさに、このような「平等感」にほかならない。しかし、どんなに横並び意識が強くても、そのことが自動的に事実としての結果の平等に結びつくわけではない。一例をあげれば、画一的な教育が、「結果の平等」のよく知られる事実として非難される一方で、そうした教育がもたらす事実としての結果の不平等(だれがどれだけの教育を受け、どのような教育を受けた人びとがどのような社会的な地位に就いているか)にまで目を向けて議論が起こらない。形式的に処遇が同じであることを確認すれば、横並びに安心してしまって、事実としての平等の検証に向かうことなく平等を問う意識は満たされてしまうのである。
しかしながら、教育の世界に限らず、「結果の平等」が実現していないことは、すでに数々の研究が実証的に明らかにするところである。所得格差が拡大していることを示す橘木俊詔の研究や、職業的地位の再生産が生じていることを示した佐藤俊樹の論考などである。さらにいえば、公務員や教員などの一部を除き、すでに日本の企業社会では横並びの集団主義や日本版「結果の平等」の理解とはほど遠い、厳しい能力主義的な競争が繰り広げられているという見方もある。
ところが、私たちの「平等感」は、こうした不平等の実態(事実)に根差すよりも、処遇の画一性に目を向ける日本版「結果の平等」に横滑りしてしまう。というのも、戦後の私たちは、平等・不平等を問題にするとき、実態よりも、感覚としての「平等感・不平等感」にしたがうことに慣れ親しんできたからである。
その原因の一端は、同じ会社や学校、同じ業界内といった閉じた空間の中で主たる競争が行われてきたために、人々はその集団内部における処遇の差異に関心を向けてきたことにある。例えば、自分とかけ離れた人びととの違いではなく、同じ集団に属する身近な人との微妙な差異が気になるのは、社会全体の不平等の実態よりも、「不平等感」がベースにあったからである。同じ会社内、同じ学校内、同じ業界内といった、閉じた空間の中で競争が繰り広げられたことにより、処遇の形式に目が向けられるようになった。その結果、個々の会社や学校や業界を越えたところにある、不平等の実態を問題にするのではなく、閉ざされた競争空間の中での処遇の微小な差異が問題にされてきたのである。こうして、横滑りした「結果の平等を問う」意識は、社会大の事実としての不平等を不問にしたまま、閉じた共同体的競争空間の中では「個人の先駆性」を抑圧するものとして作用しつづけた。
この閉じた共同体的空間における横並び意識を解体することが、結果の平等から機会の平等へという提言である。ところが、日本版・結果の平等の見方では、解体の過程で事実としての結果の不平等がどれだけ拡大しているか、それがどのような問題をはらんでいるのかということには目が届かない。一九六〇年代のアメリカほどではないにしても、現在の日本においても、特定の階層の人びとの不利な状況が再生産される「負の遺産」の蓄積が始まっているのかもしれない。そうだとしたら、結果の平等から機会の平等へという「発想の転換」は、思わぬところで足下をすくわれてしまう。そろそろ私たちは、これまでの状態を過度な「結果の平等」と見なしてしまう日本的「平等感」の危うさに気づくべきである。
IV
ところで、「自己責任社会」の担い手は、金子勝の表現を借りれば、「強い個人の仮定」に基づく個人といえる。経済における「強い個人」とは、利益を合理的に見通すことのできる経済学の教科書に登場するような「合理的経済人」であり、政治の領域では市民社会の担い手になれるような、これまた政治学の教科書に出てくるような公民的モラルを身につけた「市民」である。
「強い個人の仮定」は、だれもが強い個人になれることを前提としている。そして、強い個人であればこそ、「自己責任」を担いうると想定される。こうして、循環論法的に、次のような結論が導かれる。すなわち、「強い個人の仮定」を基盤に構想される自己責任社会では、強くなれないのは、個人の責任である、と。つまり、「強い個人の仮定」は、個人の行為の結果を自己責任に帰することをあらかじめ前提として織り込み済みなのである。
しかしながら、どのようにすれば、「強い個人」は誕生するのか。自己責任社会の担い手たる「強い個人」の形成の問題に、ひとつの政策的な解答を与えているのが、教育改革の議論に示される「生きる力」と個性尊重の教育である。
中央教育審議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」には、「[生きる力]は、自ら学び、自ら考える力など、個人が主体的・自律的に行動するための基本となる資質や能力をその大切な柱とするもの」であるとの基本認識が示されている。この認識に明瞭に示されているように、「自ら学び、自ら考える」個人こそが、「主体的・自律的」に行動できる「強い個人」である。
さらに個性尊重と「生きる力」の育成をめざす教育改革プランでは、この「強い個人をつくり出す手だてとして、学ぶ意欲や興味・関心を育てることが重視されている(『教育課程審議会答申』)。そしてその具体的な方法として、生徒の「意欲・関心・態度」を評価する「新しい学力観」に基づく評価法がすでに導入され、二○○二年からは生徒の体験的な学習・問題解決的な学習を図る「総合的学習の時間」がさらに取り入れられることになった。
このような関連を図式的に示せば、次のようになる。子どもに意味もわからないまま無理やり知識を詰め込むのではなく、子どもの意欲や興味・関心を高めるように教育を変えていくことで、「自ら学び、自ら考える」個人、「主体的・自律的」に行動できる個人を育てることができるという理解である。だからこそ、子どもにとって学ぶ意味のわからない知識を押し付けるより、子どもの生活との関連を重視した。体験的学習のような方法がよしとされるのである。
私の見るところ、この人間モデルの基盤を提供しているのは、心理学、より正確にいえば教育心理学である(なお、心理学と教育心理学との違いは、後者の場合には、心理的なメカニズムの解明にとどまらず、発達論的な観点からの望ましさについての仮定が忍び込みやすいことにあると考える)。自らの興味・関心に従い、自己実現をめざす、意欲あふれる個人、「自ら学び、自ら考える」個人一「内発的な動機づけ」にしたがった。自己啓発的な人間のモデルが、理想の教育がつくり出す「強い個人」である。
私たちがこのような個人の形成モデルを広く受け入れるようになった背景には、世俗に流通し単純化して理解された、教育心理学の学習モデルが提供する望ましい個人についての了解がある。
人びとが何かを行おうとするとき、その動機がどれだけ心の内側から発するものか。教育心理学の用語を使えば、「内発的に動機づけられているか」どうかによって、私たちの社会はその行為を価値づけることに慣れ親しんできた。強制や慣習に従うよりも、自発性が尊ばれる。金儲けや権力・名声の獲得といった、自分の外側にある目標をめざして行動するよりも、自分自身の興味・関心に従った行動のほうを望ましいと見る。個性を尊重する社会では、自分の内側の奥底にある「何か」のほうが、外側にある基準よりも、行動の指針として尊ばれるのである。個性尊重とセットになって語られることの多い自己実現も、自分の内側の「何か」が満たされた(to fulfill)状態である。個性の尊重とは、このような自己の内側にある「何か」を大切にする考え方にほかならない。個性の尊重と個人の自立を求める私たちの社会は、ますます個人の心の内なる声に価値を置こうとしている。
このように、私たちの社会を突き動かすルールの源泉に、教育心理学の提供する人間の行動モデルや学習モデルがある。その影響の一端は、子どもたちにとって意味のある学習を求める昨今の教育界に深く広く浸透している。
「何のために勉強するのか」「この知識は何の役に立つのか」。教育改革や子どもたちの学習離れをめぐって、子どもの年齢を問わず、このような問いが頻繁に登場するのも、裏返せば、学習の意味が問われているからであり、意味ある学習が求められているからである。しかし、実のところ、そもそもこうした問いにだれもが納得のいく解答などあるはずがない。突き詰めれば、それほど「哲学的な」問いだともいえるのである。にもかかわらず、意味への性急な問い掛けは跡を絶たない。学習の意味や教育の意味を求める問いの広がりは、興味・関心にしたがった。「自ら学ぶ」学習を望ましいとする学習観が、社会の隅々にまで広がったことを示している。
世俗に流通した俗流・教育心理学の学習モデルは、ひとまずこうした意味への問いかけを、各人の興味や関心に投げかけることで解消しようとする。面白いと感じるかどうか。楽しいかどうか。各人の興味や関心に「意味の問い」を振り向けることで、感性のレベルで(裏を返せば、理性的な納得に基づくのではなく)、とりあえず解答したことにするのである。面白い/つまらない、楽しい/苦痛、すぐ役に立つ/役に立ちそうもない「面白くて楽しくて役に立つ授業が求められるのは、性急に意味を求める問いが社会に充満していることの裏返しである。
しかし、俗流・教育心理学の学習モデルは、あくまでも個人のモデルであり、せいぜいが教師一生徒関係といったミクロな社会関係までにしか目を向けない。個人をとりまくより大きな社会構造の変化や社会関係によって、人々がいなかる制約を受けているかといった側面への関心は希薄とならざるを得ない。優れた教師なら、どの生徒の意欲や関心も高められるはずだといった教育学的理想主義も手伝って、人びとをとりまく環境の制約や社会の変化には目が向かなくなるのである。
だが、だれもが興味・関心・意欲を持てるのか。それらをもとにつくられる「強い個人」になるために、だれにでも「機会の平等」が保証されているのか。どの子どもの興味・関心を高められる優れた教師はどれだけいるのか。優れた教師のもとでも、興味・関心・意欲を感じられないのは、自分が悪いせいなのか。これらの問いに、俗流・教育心理学のモデルは答えない。
(対谷剛彦「『中流崩壊』に手を貸す教育改革」による)
問1.
本文では、「結果の平等」について述べているが、それに関して次の問に答えなさい。
[1]日本版「結果の平等」とは何か、50字以内で説明しなさい。
事実としての平等をないがしろにした、横並び意識とその結果にいたるプロセスの形式的な画一性を指す。
問2.
IVで述べている「強い個人」とは何か、100字以内で説明しなさい。
議論の整理→一文目で結論、二文目で追加説明。
問題発見→不要
論証→不要
解決策or結論→不要
解決策or結論の吟味→不要
「強い個人」とは、自己責任社会で生き抜ける存在である。個人の行為の結果を自己責任で考えることができ、強制や慣習に従うのではなく、内発的な動機付けに従って行動する、自己啓発的な人間のモデルを示す。
問3.
個性の尊重と「生きる力」の育成をめざす教育改革プランについての筆者の見解を300字程度で述べ、それに対するあなたの考えを400字以内で論じなさい。
筆者の見解
議論の整理→不要
問題発見→出題中の問題を整理
この教育改革プランは「強い個人」を育成するプランのことを指し、「強い個人」とは、自ら学び、自ら考えることで主体的・自律的に行動できるモデルと定義されている。
論証→(2)の原因を整理
この教育プランは世俗に流通し単純化された教育心理学の学習モデルにより定められている。世論では自ら学ぶのが良しという価値観が根底にあるため、「意味のある学習」を個人の興味・関心に結びつけて単純に結論づける傾向にある。しかし、このモデルはあくまでも対個人であり、大きな社会構造の変化や社会関係によって生じる制約についての関心は希薄である。
解決策or結論→結論
そのため、誰もが提供される教育に対して興味・関心・意欲を持つ「機会の平等」は保証されていないと主張している。
解決策or結論の吟味→不要
計299字
【私の見解】
議論の整理→不要
問題発見→一文目
私は、「学んだ知識が将来的にどう活きるのか」に重点を置いた学習を促すべきだと考える。
論証→具体例を含めて記載
例えば、具体的に微分積分を例に挙げる。実際に微分積分を使う職業として、エンジニアが挙げられる。工業製品を設計する際の強度計算や材料の使用量を概算する時に必要となる知識である。「将来微分積分を使うことなんてないだろう。だから勉強する気が起こらない」という理屈で考える子どもが車好きだった時に、「自分が好きな車を設計する際にこの知識が使われる」と知って微分積分への興味を取り戻す可能性は高いのではないか。
解決策or結論→結論
従って、教育の場面では、「何の役にたつのか」が明確になった時に、興味・関心の幅が広がる可能性を重視するべきだ。
解決策or結論の吟味→「強い個人」を育てることへの意見
全ての子どもは、自ら学び、自ら考えられる能力を生まれながらに有している。ただ、学習によって得られる知識が自分の将来に結びつくことを知らないだけだ。そのきっかけづくりが現代の教育に求められていると考える。
計398字










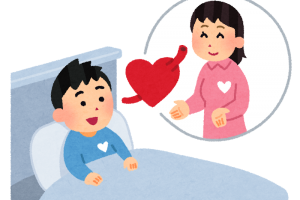



コメントを残す