【2009年 慶應義塾大学 経済学部】
■ 設問
A.
企業にとっての「年功制」の長所と短所について、課題文をもとに200字以内で説明しなさい。
B.
中学校教諭の給料は「年功制」が主流であるが、これを「能力給」に替えた場合どのようなことが起こると考えられるか。課題文のみにとらわれず、良くなる点と悪くなる点の双方に触れながら、能力給の是非についてあなたの考えを400字以内で書きなさい。
■ 答案構成
A.
このような場合、まず
1. 年功制の定義
を固めた上で、
2. 年功制の長所
3. 年功制の短所
に言及する5STEPの議論の整理の「共通の前提」「それぞれの相違点」の応用型を使うと良い。
B.
これは、5STEPを使って解くべき問題。
1. 議論の整理→ 年功給と能力給の違い
2. 問題発見→ 能力給の問題点
3. 論証→ 能力給の問題の原因
4. 結果→ 能力給の是非
5. 結果の吟味→ 年功給との比較
■ 答案例
A.
1. 年功制の定義
年功制とは、勤務年数に従って給料が上昇する給与体系のことである。
2. 年功制の長所
年功制の長所は、研究職など成果が出るまでに時間のかかる職種において、その成果測定を時間の経過に応じて適切に行うことできる点にある。
3. 年功制の短所
一方、年功制の短所は、営業職など成果が短期的に出る業種において、成果が出ている社員に不公平感を抱かせることである。
年功制とは、勤務年数に従って給料が上昇する給与体系のことである。
年功制の長所は、研究職など成果が出るまでに時間のかかる職種において、その成果測定を時間の経過に応じて適切に行うことできる点にある。
一方、年功制の短所は、営業職など成果が短期的に出る業種において、成果が出ている社員に不公平感を抱かせることである。(157文字)
B.
1. 議論の整理→ 年功給と能力給の違い
年功給と能力給の違いは、年功給が概ね勤続年数と比例して給与が上昇する体系であるのに対し、能力給は能力に応じて給与が上昇する体系であることである。
2. 問題発見→ 能力給の問題点
ここで、能力給の問題点としては、成果が短期的に測りにくい業種において導入する際に、短期的な尺度での給料決定を行い、業務に歪みが生じることである。
3. 論証→ 能力給の問題の原因
たとえば、中学校教員についていえば、中学校の教員の教育成果は、本来短期的に測れるものばかりではないが、この評価基準を生徒の成績や資格取得とすることで、成績の悪い生徒を教える動機づけが中学校教員から失われる可能性がある。
4. 結果→ 能力給の是非
このように能力給は、その測定方法いかんによっては、教育の本来的意義を損ないかねない危険性がある。
5. 結果の吟味→ 年功給との比較
一方、こうした数値評価が実施されない職場もまた、意欲ある教員から意欲を奪いうる。よって、私は計測方法が教育の本来的意義を損なわないよう配慮されていれば中学校教員の能力給に賛成である。
年功給と能力給の違いは、年功給が概ね勤続年数と比例して給与が上昇する体系であるのに対し、能力給は能力に応じて給与が上昇する体系であることである。
ここで、能力給の問題点としては、成果が短期的に測りにくい業種において導入する際に、短期的な尺度での給料決定を行い、業務に歪みが生じることである。
たとえば、中学校教員についていえば、中学校の教員の教育成果は、本来短期的に測れるものばかりではないが、この評価基準を生徒の成績や資格取得とすることで、成績の悪い生徒を教える動機づけが中学校教員から失われる可能性がある。
このように能力給は、その測定方法いかんによっては、教育の本来的意義を損ないかねない危険性がある。
一方、こうした数値評価が実施されない職場もまた、意欲ある教員から意欲を奪いうる。よって、私は計測方法が教育の本来的意義を損なわないよう配慮されていれば中学校教員の能力給に賛成である。(397文字)





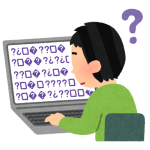





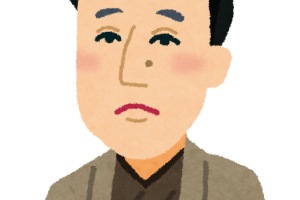

コメントを残す