問題1
資料1~5の内容を参考に、各資料に共通する論点、立場の異なる論点、あなたが重要と考える論点などを挙げつつ、グローバリゼーションが世界の政治・経済にもたらしている変化について論じてください。(800字)
問題2
資料1~5は、いずれもグローバリゼーションの拡大と深化が進む現代の特徴を論じたものですが、問題2では未来についての予測を問います。資料1~5のいずれか一つを選択し、その資料が取り上げているテーマに関して、次なる「バージョン」もしくは「波」の特徴がどのようなものになるかを予測し、その新しい「バージョン」もしくは「波」の到来によって世界の政治・経済はいかに変化するのか、あなたの考えを述べてください。(解答用紙の欄に資料1~5のどれを選択したのか、番号を記入してください。)
・ 問題の読み方
問題一は「変化について”論ぜよ”」とあるので、グローバル化が世界の政治・経済にもたらす影響を5STEPsで書く必要がある。
議論の整理……グローバル化とは何か? 各資料に共通する論点、立場の異なる論点、あなたが重要と考える論点などを挙げる。
問題発見……グローバル化の中での問題点を挙げる。(複数挙げて現代的意義を持つ一つに絞る。)
論証……その原因を分析する。
解決策or結論……その根本的な原因を潰す解決策or結論なり結果なりを考える。
解決策or結論の吟味……その解決策or結論なり結果なりを吟味する。
問題二は問題一の内容を踏まえて、次なる「バージョン」もしくは「波」の特徴がどのようなものになるかを予測し、その新しい「バージョン」もしくは「波」の到来によって世界の政治・経済はいかに変化するのかを書くと良い。
基本的に5STEPsを使うことになるが、主な構成は以下の様な形になる。
議論の整理……今までのグローバリデーションとこれからのグローバリゼーションの潮流まとめ
問題発見……次なるバージョンの到来によって世界の政治経済はどのような影響を受けるか?
論証……その原因の分析
解決策or結論……その根本的に原因を潰すための解決策or結論
解決策or結論の吟味……解決策or結論の吟味
・ SFC小論文で求められている解答への指針
基本的に政治経済のことを考える時に、一般的には考えない要素を入れると良い。
たとえば、フランス革命以降、政教分離原則が徹底し、政治の世界に宗教が関わらなくなったが、近年ではISISなどの暗躍により政教一致国家が誕生しようとしている。このような背景を鑑みて、宗教コミュニティーが世界の政治経済に及ぼす影響についてグローバル化と絡めながら論じると、SFCが得意とするところの学際的分野に近づく。
・ 模範解答
「問題1」(100/200)
議論の整理(20/100)→
共通の前提(10/20)……
共通の前提として、グローバル化が抵抗を受けながら進んでいくものであることを示せていれば10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
各資料で共通している論点は、「グローバリゼーションというものは、ある程度の過程を経ながら進んでいくものだ」ということである。グローバル化は、気づいたら進んでいたというものではない。何らかの抵抗を受けながら進んでいくものなのだという認識が、各資料の中で共通している。
……これは課題文を読むまでもなく、問題文を読めばわかる。以下、引用する。
資料1は、ニューヨークタイムズの名物コラムニスト、トーマス・フリードマンが執筆したベストセラー『フラット化する世界』の抜粋です。フリードマン氏は、巨視的な視座から、国家がグローバル化した「1.0」、多国籍企業がグローバル化した「2.0」の時代を経て、いよいよ個人がグローバル化する「3.0」の時代に入ったことを論じています。
資料2は、社団法人日本経済団体連合会(経団連)のシンクタンクである21世紀政策研究所のプロジェクト報告書です。同報告書では、フリードマン氏と同様に「グローバリゼーション3.0」という表現を用いつつ、日本の企業活動におけるグローバル化の歴史を3段階にわけて論じ、現代の日本企業が「グローバルの輪」と「アジアの輪」の中で活動すべきことを主張しています。
資料3は、若くしてリスク・コンサルティング会社を起業したイアン・ブレマーの新著『自由市場の終焉』の抜粋です。ブレマー氏は、グローバリゼーションの進展は、必ずしも自由で開かれた経済システムの浸透を意味しないとして、中国やロシアなどで国家による強い市場コントロールを前提とした「国家資本主義」が台頭した背景を論じています。
資料4は、国際政治学者の山本吉宣教授の地域統合に関する論文です。山本教授は、グローバリゼーションが進展する過程での地域統合の形態の変化について論じ、50年代末から70年代にかけての第一の波、80年代末から90年代後半にかけての第二の波を経て、地域統合には第三の波が到来していることを示唆しています。そして
資料5は、政治学者の岩崎育夫教授がサミュエル・ハンチントンの『第三の波』を解説した文章です。ハンチントン氏は、近現代史における民主化波及の歴史的特徴を、ラテン・アメリカ諸国における植民地からの独立、ヨーロッパや日本の民主化が進展した第一の波(1828~1926年)、第二次世界大戦中から戦後にかけての第三世界における民主主義国家が誕生した第二の波(1943~62年)、そして南ヨーロッパ、ラテン・アメリカ、中東欧地域へと民主化が拡大した第三の波(1974年~)に区分して論じました。
議論の論点(10/20)……
論点として「どんなことがきっかけで変化を引き起こしたのか」があるということを示せていれば5点、「グローバリゼーションが世界的に広まったきっかけ」にも言及できてたからさらに5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
立場の異なる論点に関しては、「どんなことがきっかけで変化を引き起こしたのか」という部分だ。それは国家によってなのか、多国籍企業によるものなのか、または個人によるものなのか、それぞれ意見が異なっている。また、「グローバリゼーションが世界的に広まったきっかけ」についても、各資料で意見が異なっている。
……これについても、引用部分から理解することが可能である。
問題発見(20/100)→
論点として「誰がグローバル化への抵抗力に打ち勝ったか」を設定できれば20点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
これはつまり、「誰がグローバル化への抵抗力に打ち勝ったか」ということであり、私が重要だと考える論点だ。
……例によって、主語と動詞がある疑問文の形で問題提起をする。(「グローバル化の抵抗力に打ち勝つことの何が問題なのか?」などという問いと異なり、価値中立的にするためである。)
論証(20/100)→
論理的に書けていれば5点、構造を捉えられていれば5点、新規性5点、緻密性5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
グローバリゼーションが世界に与える影響は、人々が少しずつ国境というものを感じなくなり、世界が単一の場所になっていくことだ。それにより、国同士で人々が行き来しやすく、移住しやすい環境になるという変化をもたらす。もし自分の国の政府に不満があって、多くの人々が簡単に移住をするようになると、これは政治面に大きな影響を及ぼすことになる。また経済に与える変化については、国境がなくなることによって市場が拡大することである。今までは国内でしか売れなかった商品が、グローバル化によって世界中で売れるようになる。良い商品を作っていればその分売れるので、チャンスが増えることに繋がる。
……ここでの記述は、リンガメタリカなどで背景知識を得ていれば、執筆者が何の手本もなく書くことも十分可能だが、一応各課題文から根拠となる部分を引用する。いずれも最終段落からの引用となる。
資料1
グローバリゼーション3.0がこれまでの時代とまったく異なるのは、サイズを縮小し、世界をフラット化し、個人に力を与えたことだけではない。もう一つの違いは、グローバリゼーション1.0と2.0の牽引力は欧米の個人やビジネスだったという点だ。たしかに中国は18世紀も世界有数の経済大国だったが、グローバル化とそのシステムの改良は、欧米の国や企業や冒険家が主に進めていた。しかし時代が進むにつれて、この傾向はどんどん薄れていった。なぜなら、世界をフラット化して縮めていくグローバリゼーション3.0は、日増しに欧米の個人だけではなく、(非欧米、非白人の)多種多様な個人の集団によって動かされるようになっている。フラットな世界のあらゆる国々の個人が力を持ち始めている。グローバリゼーション3.0によって、多くの人々がゲームに直接参加できるようになり、あらゆる肌の色の人間が役割を果たすようになっている。
資料2
グローバリゼーション3.0になって、各国ともグローバルな輪の一つの中核的な地域面になろうとして、世界の企業進出を呼び込んでいる。そして、世界の巨大企業はグローバルな輪を完成するために、強者は買収・提携策による「世界再編」を進めているし、弱者はグローバルプレーヤーと手を結んでグローバルの輪から外れないように努力している。日本企業は世界再編を視野に入れた企業戦略を考える必要があり、日本市場だけで乱立して戦っていては、海汰されてグローバリゼーションの波に飲み込まれかねない。
資料3
このような状況を受けて今後の数年は、一般に自由市場資本主義のせいだとされる世界経済のメルトダウンの影響により、「賢明な規制のもとにおける民間セクターの競争は、長期的な経済成長に欠かせない」と考える人々の主張が力を弱めるだろう。この問題を念頭に置きながら、中国やロシアほか多くの国で国家資本主義が実際にどう運用されているかを理解することが非常に重要である。その強みと弱みを知り、今後わたしたちの暮らしにどのような変化をおよぼしそうかを見極めるために。
資料4
第三の波は、南ヨーロッパから始まった(1974年から)。第二次大戦後、大半のヨーロッパ諸国が民主主義体制となったなかで、ポルトガル、スペイン、ギリシヤの南ヨーロツパ諸国では軍政が残っていたが、1974年にポルトガルで民主化運動が発生して民主主義体制へと転換し、スペインとギリシャの軍政も崩壊した。この民主化の波は南ヨーロッパ地域にとどまることなく、ラテン・アメリカへと伝播して軍政や権威主義体制の崩壊へと繋がり、アフリカでも支配的であった一党独裁体制の終焉を促し、ソ連・東欧地域でも社会主義体制が終焉して民主主義体制へと転換した。南ヨーロッパ→ラテン・アメリカ→アフリカ→ソ連・東欧と世界各地を駆け巡った民主化の波が、1980年代中頃にアジアにも到達し、アジア諸国で民主化運動が爆発したのである。
結果→
影響に言及されていれば10点、影響に新規性があれば5点、影響に緻密性があれば5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
しかし、みんなが良い商品を作ろうとすると、それだけ競争相手も増えていく。
……問題文にあるように、解決策or結論を探る問題というよりは、どちらかというと影響を探る問題なので、このような書き方になる。
結果の吟味(利害関係者検討)→
チャンスに言及されていれば5点、リスクに言及されていれば5点、新規性があれば5点、緻密性があれば5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
競争相手が増えるということは、自分が負けてしまうリスクも当然増える。市場において、チャンスも増えるが同じ分だけ自分が負けるリスクも高まってしまうのが、グローバリゼーションが世界の経済に及ぼす変化である。
……資料文2の「グローバルの輪から外れないように……」という表現を参考にしつつ、このような形で書く。
「問題2」(100/200)
議論の整理(20/100)→
グローバリゼーションの説明10点、グローバリゼーションの影響10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
グローバリゼーションとは、政治的・経済的な意味で「国境が無くなり、世界が単一の場所になる」ことだ。市場において、チャンスも増えれば競争相手も増える。これが「グローバリゼーション」というものだ。
……これは、先ほど紹介した引用部でも述べられている。
資料1
グローバリゼーション3.0がこれまでの時代とまったく異なるのは、サイズを縮小し、世界をフラット化し、個人に力を与えたことだけではない。もう一つの違いは、グローバリゼーション1.0と2.0の牽引力は欧米の個人やビジネスだったという点だ。たしかに中国は18世紀も世界有数の経済大国だったが、グローバル化とそのシステムの改良は、欧米の国や企業や冒険家が主に進めていた。しかし時代が進むにつれて、この傾向はどんどん薄れていった。なぜなら、世界をフラット化して縮めていくグローバリゼーション3.0は、日増しに欧米の個人だけではなく、(非欧米、非白人の)多種多様な個人の集団によって動かされるようになっている。フラットな世界のあらゆる国々の個人が力を持ち始めている。グローバリゼーション3.0によって、多くの人々がゲームに直接参加できるようになり、あらゆる肌の色の人間が役割を果たすようになっている。
問題発見(20/100)→
問題提起10点、問題提起の新規性5点、問題提起の緻密性5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
そのうえで、グローバリゼーションが国家によって強く押し進められてきた。さらには、資料3で書かれているように、グローバリゼーションを利用するような国家が出てきた。だが国民が国家に対して、常に忠誠心を持っているとはいえない。政治への不満から海外へ移住してしまうような、忠誠を誓っていない国民も多い。
次なる時代の到来によって、これからは、宗教資本主義の台頭が予想されるだろう。
……これも、基本的には先ほどの問題の引用部で述べられている。そのうえで、こうした国家資本主義国家がかならずしも国民の支持を受けていないことは、逆説的ではあるがこうした国家においてえてして民主的な選挙が成立していないことからもわかる。
資料3
このような状況を受けて今後の数年は、一般に自由市場資本主義のせいだとされる世界経済のメルトダウンの影響により、「賢明な規制のもとにおける民間セクターの競争は、長期的な経済成長に欠かせない」と考える人々の主張が力を弱めるだろう。この問題を念頭に置きながら、中国やロシアほか多くの国で国家資本主義が実際にどう運用されているかを理解することが非常に重要である。その強みと弱みを知り、今後わたしたちの暮らしにどのような変化をおよぼしそうかを見極めるために。
論証(20/100)→
問題提起の根拠10点、新規性5点、緻密性5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
宗教がなぜ力を持つのかは、人は自分から進んでその宗教を信仰しているからだ。つまり、個人が強い忠誠心を持っている。そこから、今後力を持った何らかの宗教勢力が、グローバル化社会において、信者の強い忠誠心をベースに大きな影響を与えることが予想される。
……ここでは、国家資本主義国家の興隆の一方で、宗教が力をもちうる理由について述べている。
結果・結果の吟味→
他の解決策との比較10点、利害関係者検討10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1
グローバリゼーションによって競争至上主義が生まれる。将来的に、格差がさらに激しくなった時代が訪れる。そのときに人は、宗教を必要とするだろう。かつて日本で飢饉が起きたときや政治が弱体化したとき、人々は仏教に救済を求めた。宗教は弱者にとって救いになることがある。宗教がその人にとって導いてくれるものであることを考えると、政府よりも国民の忠誠を得られやすいために大きな影響力を持つことが考えられる。
……問題文からいって、影響を考慮する類のものなので、書き方はこのような形になる。






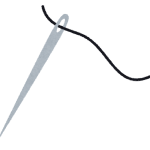



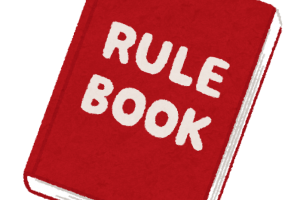



コメントを残す