・ 問題文
問題
以下にあげた二つの文章は、新渡戸稲造(1862~1933)と内村鑑三(1861~1930)のそれぞれの著作『武士道』(1900)と『代表的日本人』(旧版1894,決定版1904)の一部です。二つとも原文は英語で書かれています。
二冊の本が出版された当時一それは明治維新から30年あまりがすぎた19世紀末でしたが日本はようやく近代化が軌道にのり,新興国家として国際社会で頭角を現しつつありました。日清戦争から日露戦争にいたる頃です。当時の世界秩序を主導していた欧米諸国の人々は,アジアに生まれた新しい近代国家である日本にたいして,好奇心と警戒感をもっていました。
新渡戸と内村は欧米の読者に日本がいかなる国であるのかを理解してもらおうと,英語で日本の文化や歴史について説いたのです。二人の意図は実を結んで,彼らの著書は海外に多くの読者を獲得し,今日にいたるまで読まれ続けています。特に新渡戸の著書は,日露戦争の後,アメリカでベストセラーになりました。-
現在。当時と比べて日本から世界各国へと発信される情報量は格段にふえました。けれどもまた。日本についての理解は深まったとはいえない面もあります。むしろ誤解がひろがっているといわざるをえないところもあります。はたして100年前に新渡戸や内村が語ったような熱意と説得力で私たちは国際社会にたいして語りかけているでしょうか。
そこで、今日は,現在の日本がいかなる国であるのか。歴史をふまえつつ,優れたところや悪いところ,問題点,これからの展望などについて。必ず具体的な事例(人物、事件,流行。都市,環境,経済,技術など)にそくして,外国の人に対して説明してもらいたいと思います。新渡戸と内村は欧米の読者にむけて書きましたが、現在の世界では欧米の人だけに語ればよいというものではありません。今回はみなさんにまず語りかける相手の国の人々を選んでもらい、その相手国の事情も勘案したうえでその国の人たちに,日本について説明し。論じてもらいたいと思います。二人の文章をよく読んだうえで,みなさんなりの発想と語り口で。自由に書いてください。新渡戸と内村の文の要約や解説、引用はしないでください(冒頭に語りかけた国の名前を明記し1000字以内)。
そのうえで。別に,どうしてその国の人々にむけて書いたのか。どのような意図で。何を主眼として書いたのかを説明してください。(500字以内)
・ 問題の読み方
“二人の文章をよく読んだうえで,みなさんなりの発想と語り口で。自由に書いてください。新渡戸と内村の文の要約や解説。引用はしないでください(冒頭に語りかけた国の名前を明記し1000字以内)。”というこの問題は、典型的な5STEPsを用いた問題である。
だが、オーソドックスでない部分としては、”新渡戸と内村の文の要約や解説。引用はしないでください”という一文がある。つまり議論の整理の段階で、自ら考えた論と一般的な論の共通の前提・共通の理想・議論の論点(≒方法論の相違)をしっかりまとめないといけないということである。その上で、問題発見・論証・解決策or結論・解決策or結論の吟味へと移っていかなければならない。
”そのうえで、別に,どうしてその国の人々にむけて書いたのか。どのような意図で、何を主眼として書いたのかを説明してください。(500字以内)”という部分については、結論・根拠・具体例を用いて書くほか無いだろう。結論でどこの国の人に対して書いたかを書き、根拠で問題文中で指示されているように、”どのような意図で。何を主眼として書いたのかを説明し”、その上で文字数が足りなければ適切な具体例を出せば500字が埋まる。
・ SFC小論文に求められる解答の指針
経済学的な分析を地球環境について行うなど、学際的な応用分野について言及すると良い。なぜなら、SFCはそうしたことができる人材を求めているからである。小論文として書きやすいのはやはり経済学の応用分野で、厚生経済学・行動経済学・教育経済学などの知見をリンガメタリカやアカデミックなどを通じて習得すると良い。
・ 模範解答
「問1」
問題提起→
戦後の日本は、経済大国と言われるまでに成長してきた。しかし、その成長の裏で、公害などの環境問題を多く引き起こしている。現在地球で暮らす我々のためだけでなく、我々の子孫のためにも、環境問題は解決しなければいけない。これについて、アメリカに対して語りかけたい。
戦後の日本の成長は、それに伴い多くの環境問題を引き起こした。しかし、その日本の技術的・経済的進歩は、現代の我々の生活を豊かにしていることも事実である。新幹線などの交通技術の発達や電化製品などが作られたことによって、日本人の生活は便利で快適になった。また、医療技術の発達によって、人々がより健康に、そして長生きするようになった。現在も、さらなる快適さ豊かさを求めて、開発が続いている。だが、このような発展の裏でそれぞれを実現させるべく、大量のエネルギーや資源が使われた。つまり、多くの自然環境が破壊されてきた。
日本は高度経済成長において、自然環境を軽く見た経営によって公害を経験した。現在も日本では、原発や二酸化炭素排出量の問題など、環境に対する問題は多い。
その中でも、二酸化炭素排出量の問題は重大である。二酸化炭素排出量が多ければ、地球の気温が上昇する。それによって、海面の上昇や異常気象、さらには生態系の変化などといった問題を引き起こすからだ。これらの問題は、現在の我々の生活に対し悪影響を及ぼすだけではない。我々の息子や孫に対して、より深刻な問題を残してしまう。
論証→
なぜ、こうした問題が起こるかといえば、こうした汚染物質の排出が人々の思うがままに任させているためである。
解決策or結論→
そこで、各自治体の中で無駄な電力の使用を抑え、全体の二酸化炭素排出量を抑える仕組みを提案する。つまり、先進国や企業間で設けられている「排出権」と「排出権取引」を、各自治体にも設ける。それらを各自治体へ導入することによって電力の使用量を意識させ、それぞれの家庭の積極的な節電を促すことが可能になる。具体的な仕組みについては、まず、役所など行政側が自治体に見合った排出量の制限をする。そして、振り分けられた自治体全体の排出枠を、各家庭で話し合いをし合意形成した後、各家庭へ振り分けるようにする。制限を超えてしまった家庭については、超えていない家庭から排出枠を買わなければいけないという方法をとる。
解決策or結論の吟味→
しかし、この、他の家庭から排出枠を買うという方法を使用する際に、注意しなければいけないことがある。お金を持っている家庭が、持っていない家庭からむやみに排出枠を買い取るということが予想される。これを防ぐためには、各家庭の状況を自治体で管理することが大切だ。本当に制限を超えた場合のみ、他の家庭から排出枠を買い取ることを許すというシステムが重要だ。この仕組みによって、各家庭の電力使用量を意識させることができる。そして、各家庭の積極的な節電につながり、二酸化炭素排出量を抑えることが可能である。
「問2」
結論→
私はこの文章を、アメリカに向けて書いた。
根拠→
その理由として、現在、二酸化炭素排出量が世界で一番多いのがアメリカだからだ。アメリカは国土が広く、産業も活発である。また、生活水準も高い。アメリカのような大国がこれから先も同じ方法でエネルギーや資源を使い、成長を続けると、地球環境へ大きな影響を与えてしまう。我々や、我々の息子や孫のためにも、できるだけ環境に悪影響を及ぼさない成長の方法を考えていかなければいけない。そのような観点から、アメリカという大国を選んだ。





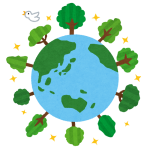
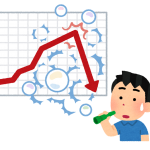
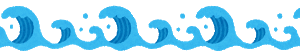


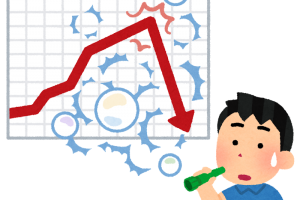

コメントを残す